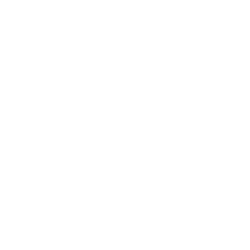先週末は、自転車イベント「那須高原ロングライド」に参加してきました。
チャレンジ70km。
5時間くらいかけて山岳コースを走り抜けます。
体力的に限界です。
今回は暑さが限界でした。でも自転車に乗っていると強制空冷が働くので、まわりの想像ほどではないんですね。走ってる時は良いのですが信号やエイドステーションで自転車が止まると、途端に汗が吹き出します。
心肺系も限界です。ハアハア呼吸が上がり心拍数がドキドキ、苦しさの極限です。
筋肉も限界です。今回はかろうじて脚が攣らなかったけど、よく攣ります。
消化器系も限界です。途中に何ヶ所かあるエイドステーションでは飲み物や食べ物がたくさん出ます。エネルギーが相当消耗するので、いくらでも入ります。というか入れないと「シャリバテ」で動けなくなってしまいます。それを受け止める胃腸も結構な負担です。
心も折れます。やっている最中は、「なんて俺はバカなんだろう。こんな苦しい思いを好き好んでやっているんだ!?」と自問自答します。妻からは「あなたは相当Mね!」と揶揄されます。
でも、苦しい登り道でもいつかは終わるんだと思いながら意地で頑張ります。
今回は、途中ポイントでの時間切れ足切りもまぬがれ、どうにか完走ゴールしました。
一日経った翌日も、まだ身体の節々に違和感があり、筋肉に乳酸が残っているような気がします。
あれだけ過酷な試練を身体に与えれば、それに順応するために身体の中に何か変化が起こっているにちがいない、、、そんな想像を巡らせます。
このように、自分の身体に過酷な試練を与えることは、若いころからやってきました。私は「合宿」が好きなんだと思います。
十代の頃は、中学から大学まで、運動クラブに参加してきました。
中学では柔道部。いつもと同じ中学の体育館で夏合宿をやりました。普段の練習より少し長いくらいで、それほど印象には残っていません。
高校山岳部の夏合宿は強く印象に残っています。
1年生の夏合宿は東北の飯豊連峰。
2年生では北アルプスの裏銀座縦走(立山〜薬師岳〜三俣蓮華〜槍ヶ岳〜上高地)。
3年生では南アルプスの南部縦走(塩見岳〜荒川岳〜聖岳)。
いずれもディープな、ちょっとやそっとでは実現できないハードなコースです。
高校レベルでよく行ったな、今なら遭難を恐れてとてもできないだろうと思います。
高校教師の顧問と、卒業した大学生のOBが一緒に参加してくれたからできたと思います。
大学ではアメリカンフットボール部。夏休みに4−5泊かけて高原の涼しい合宿所に泊まり込み特訓練習をします。山岳部の夏合宿はそれ自体が達成すべき目的だが、大学のフットボールは秋のリーグ戦に勝つことが目的だから、夏合宿はその準備手段という違いはあります。
大学の教員になってから田村研究室の学部生・院生たちと「ゼミ合宿」を2泊3日で行いました。学生たちの卒業論文を集中的に指導します。きっと学生たちにとってはハードな体験だったと思います。
大学を退職して、開業してからは、若いセラピストたちにグループ・スーパーヴィジョンを始めました。その一環として夏に草津の別荘で2泊3日の合宿をやりました。
私にとって、「合宿」とは次のような要素が当てはまります。
- 日常生活とは別の場所で、普段はできないような特別なことを集中して行う。
- 夏にやる。
- 日帰りではなくて、何泊か寝食を共にする。
- ハードで苦しい。
- ひとりではとてもできない。仲間がいるからなんとかできる。
- それを通り越すと、自分の何かが変わる(成長する)。
このような私の体験に基づいて、今は「ジェノグラム合宿」を主宰しています。
今年は8月に2回、9・10月は学会や海外出張が忙しいのでお休みして、11月に1回開催します。
上記1〜6の要素を満たしていると思います。身体的にはハードではないけど心理的にはもしかしたらハードかもしれません。というのも、普段あまり使っていない心の領域を使うからです。
それを経験して「自分の何かが変わる(成長する)」というのも十分に期待できる効果だと思います。